|
���w�ҁ��E�C���A���E�V�F�[�N�X�s�A William Shakespeare
�@�@�@���E�����j��ő�̌����
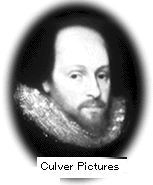
|
�E�C���A���E�V�F�[�N�X�s�A�F1564�N4��23���`1616�N4��23��
�E�C���A���E�V�F�C�N�X�s�A�iWilliam Shakespeare�j�́A�C�M���X�̌���ƁA���l�B
���E�����j��ő�̌���ƂƂ����A�S���E��ʂ��č�i���㉉����A��i�Ɍ��ꂽ
�l���̃L�����N�^�[�͂��̂܂܃��[���b�p�ߐ��̓T�^�I�Ȑl���̐��_�j���`����Ă�B1564�N4��23���ɃC�M���X�̃X�g���g�t�H�[�h�Ƃ������ŁA��v���W���������A���[�E�V�F�C�N�X�s�A�v�Ȃ̒��j�Ƃ��Đ��܂�A�z�[���[�E�g���j�e�B����Ő������B�r�{�Ƃ��đS37��i������A�傫�����ނ���Ɨ��j���A�쌀�A�ߌ��ɕ������B
�l��ߌ��Ə̂����̂́u�}�N�x�X�v�iMacbeth�j�A�u�n�����b�g�v�iHamlet�j�A�u���A���v(King Lear)�A�u�I�Z���v(Othello)�B�����̍�i���ł������A�C�M���X�̔ɉh��S���Ă����G���U�x�X�ꐢ�������i1603�N�j���Ă���B���Ƃ��Ă�1609�N�́u�\�l�b�g�W�v���L���B
|
�@
�w���~�I�ƃW�����G�b�g�x�̑听���ŁA�Ăу����h�������E�����ẲԌ`��ƂƂȂ����E�C���A���E�V�F�[�N�X�s�A�́A���X�Ƙb���ݏo���Ă������B�w���`���|�h�x�A�w�Ă̖�̖��x�A�w���F�j�X�̏��l�x�B������1601�N�w�n�����b�g�x�������B
�u�����邩�A���ʂ��A���ꂪ��肾�v�A�u���\�ȉ^���̐Ɩ��ς��E�Ԃ̂������̂��A�@����Ƃ����̍r�C�Ɛ키�����E�E�E�v�B�u������A������A���̂܂̓��I�l���͕����܂��e�@�t�A�����Ȗ��҂��B�v�|�w�}�N�x�X�x
���E���ς��n�߂Ă����B1603�N�A��̎��オ�������B���@�|�W���E�N�C�|���A�G���U�x�X�ꐢ�����B�C�M���X���x���������傫�Ȓ����|�ꂽ�B
�u���̒n��ɍ݂��̂��̂́A���ǂ͗n�������āA���������������e�Ɠ��l�ɂ��Ƃɂ͈�Ђ̕��_���c���͂��Ȃ��B��X�l�Ԃ́A���Ɠ������̂ŐD��Ȃ���Ă���B�͂��Ȃ��ꐶ�̎d�グ������̂́A����Ȃ̂��B�E�E�E�E�v
1611�N�A�Ō�̍�i�A�w�e���y�X�g�x
1616�N4��23���A��������܂ꂽ���Ɠ��������A�E�C���A���E�V�F�[�N�X�s�A�͂��̐����������B���N52�B
�������g�̒��ɂ���ꂵ�݂▵���𐳖ʂ��猩�߁A�l�ԂƂ͉����A�l���Ƃ͉����Ƃ������ǂ��������E�C���A���E�V�F�|�N�X�s�A�B���̗D�ꂽ�ώ@��Ɛ[�����@�͂ɂ���Đl�Ԃ̍��������ɂ߂悤�Ƃ����ނ̍�i�́A400�N�̎����z���A�������������ƌ��p����Ă��܂��B����͎��B�N���������̒��Ƀn�����b�g�Ɠ��������ɖ��������݂�����Ă��邩��ɈႢ����܂���B
�ނ͍����₢�����Ă���̂ł��B�@
To be, or not to
be�Cthat is the question.
�s�m�������t1996�N3��5��
����
�V�F�[�N�X�s�A�̑�\��i�Ɩ�����W
���~�I�ƃW�����G�b�g
�W�����G�b�g�����~�I
�K�N�̉Ԃ�ʂ̖��O�ŌĂ�ł݂Ă�
�Â�����͎����͂��Ȃ��B
���[�����X�_�������~�I
�S�̗���Ă���؋������A
���̂悤�ɒ������Q���o�����肷��̂́B
�n�����b�g
�d�b�z���C�V���[
���������F�̔��(������)���Ђ낰�A
�I�ݒ��߂Ȃ���A���̔������z���Ă���B
�|���[�j�A�X�����C�A�[�e�B�[�Y
���͎�Ă��������A�݂��Ă��������ƁB
�݂������������킹�ėF�������B
�M���f���X�^�[��
��������]�A
��S�̎��̂͏��F�����̏h���e�ɂ����܂��ʁB
���[�[���N�����c
��]�ȂǂƐ\�����̂͋�C�̂悤�ɗ���̂Ȃ����́B�@
�e�́A���̂܂��e�ɂ����܂��ʁB
�n�����b�g
�������Ĕ��ȂƂ�������A
�����l�����a�ɂ��Ă��܂��B
�n�����b�g����K�[�g���[�h
�K���Ƃ��������́A�ǂ̂悤�Ȉ����ɂ�
�����܂��l���o�ɂ����Ă��܂��B
�n�����b�g���e�F�z���C�V���[
����ׂ����̂́A���ܗ��Ȃ��Ƃ��A������͗���B
���A������
���A
�N�ł������A�����Ă���A�킵�͂Ȃɂ��̂��B
����
���A�̉e�@�t�����B
���瑛��
���͐����A���̕��A�L���[�s�b�g�̖��
���Ƃ������̂�����A㩂ŕ߂܂���̂�����
�B
�Ă̖�̖�
���C�T���_�[���n�[�~�A
���܂ŕ������j�̖{�����낢��ǂ��Ƃ�����
�B
�܂��Ƃ̗��������₩�Ɏ��������߂��͂Ȃ��B
�d���p�b�N
�͂āA���āA�Ȃ�Ɣn���҂���ł����낤���A
�l�ԂƂ������̂́B
�\���
�����t�t�F�X�e�������}���C��
�m�b���鈢���͈����Ȓm�b�҂ɂ܂���B
�I�Z���[
�@�@���l�I�Z���[�Ɣ��l�f�Y�f���[�i�̔g�p����̕���
�@�@�@�@�@�@�@
�˃I�Z���Q�[���̌ꌹ
�Q���ꂽ�I�Z���[
���܂�āA����ꂽ���̂ɋC�Â��ʒj�ɂ́A
�����m�点�Ă�邱�Ƃ͂Ȃ�
�B
�e���y�X�g�@1611�N�A�Ō�̍�i
�v���X�y���[���l���ɂ��Č��������䎌
���̒n��ɍ݂�[�̂��̂́A���ǂ͗n�������āA���������������e�Ɠ��l�ɁA���Ƃɂ͈�Ђ̕��_���c��͂��Ȃ��B
��X�l�Ԃ́A���Ɠ������̂ŐD��Ȃ���Ă���B
�͂��Ȃ��ꐶ�̎d�グ������̂́A����Ȃ̂��B
�}�N�x�X
����
�e�w���҂��҂������A�����������̂��������ɋ߂Â��ė���B
�}�N�x�X
�l�̐��U�͓����܂��e�ɂ����ʁB
�����Ȗ��҂��B
�}�N�x�X
���������A����������A�����Ă܂�������
�E�E�E�B
�������Ĉ������Ə������݂ɁA
���̊K(�����͂�)�����藎���Ă���
�̕����u���w�̃y�[�W�v
�E�B���A���E�V�F�C�N�X�s�A��i�W�i�f��E�e���r�j������������
|
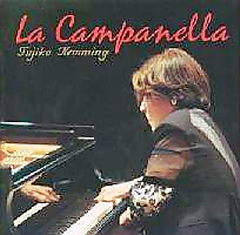
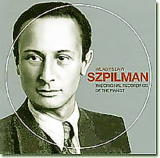

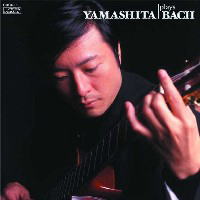

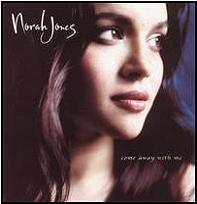 �i�ȉ��A����EMI�̃T�C�g��CD�A���o������L����q���܂����j
�i�ȉ��A����EMI�̃T�C�g��CD�A���o������L����q���܂����j

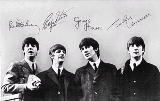


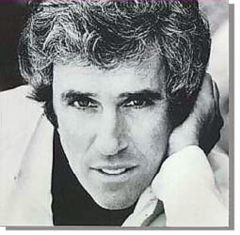
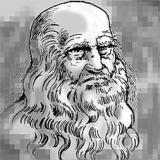



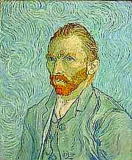
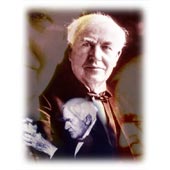


 �@�@
�@�@ �@�@
�@�@

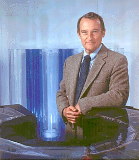

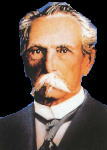


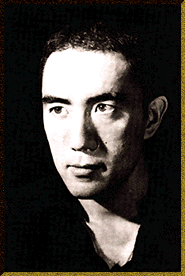
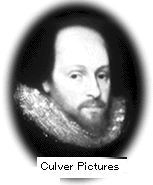

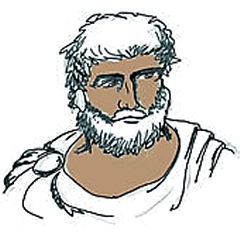
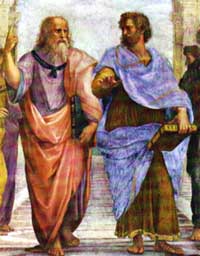

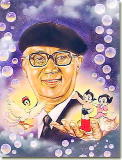
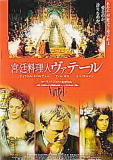

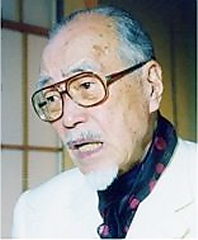
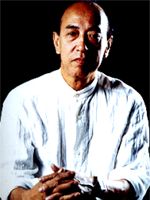

 �@
�@
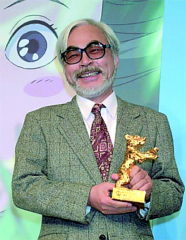
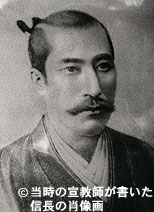


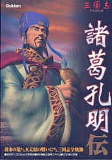
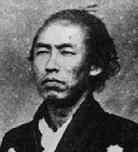




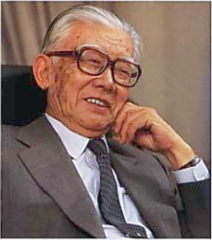 �@
�@
